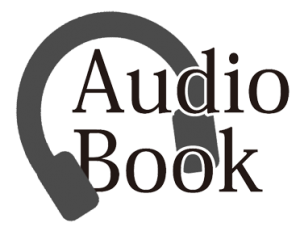
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 40 | 1 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 内容 | 336 | 小 |
| 40 | 2 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 女神(めがみ)の死(し) | 5398 | 中 |
| 40 | 3 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 天(あめ)の岩屋(いわや) | 5529 | 中 |
| 40 | 4 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 八俣(やまた)の大蛇(おろち) | 2687 | 小 |
| 40 | 5 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 むかでの室(むろ)、へびの室(むろ) | 8136 | 大 |
| 40 | 6 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 きじのお使(つか)い | 6282 | 中 |
| 40 | 7 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 笠沙(かささ)のお宮 | 4718 | 小 |
| 40 | 8 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 満潮(みちしお)の玉、干潮(ひしお)の玉 | 6659 | 中 |
| 40 | 9 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 八咫烏(やたがらす) | 8141 | 大 |
| 40 | 10 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 赤い盾(たて)、黒い盾(たて) | 3632 | 小 |
| 40 | 11 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 おしの皇子(おうじ) | 7132 | 大 |
| 41 | 12 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 白い鳥 | 9846 | 大 |
| 41 | 13 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 朝鮮征伐(ちょうせんせいばつ) | 7291 | 大 |
| 41 | 14 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 赤い玉 | 3111 | 小 |
| 41 | 15 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 宇治(うじ)の渡(わた)し | 6189 | 中 |
| 41 | 16 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 難波(なにわ)のお宮 | 8244 | 大 |
| 41 | 17 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 大鈴(おおすず)小鈴(こすず) | 6024 | 中 |
| 41 | 18 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 しかの群(むれ)、ししの群(むれ) | 5242 | 中 |
| 41 | 19 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 とんぼのお歌 | 5293 | 中 |
| 41 | 20 | 鈴木 三重吉 | 古事記物語 うし飼(かい)、うま飼(かい) | 5737 | 中 |
文字数合計 115627
名作速読朗読文庫vol.42 聖徳太子十七条憲法Professional版
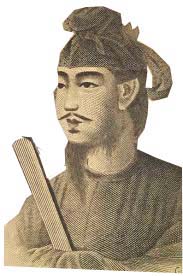
内容
十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)とは、推古天皇12年 ユリウス暦604年 に、聖徳太子が作ったとさ れる17条からなる法文である
憲法という名前がつけられているが、政府と国民の関係を規律する近代憲法とは異なり、その内容は、官僚や貴族に対する 道徳的な規範が示されており、行政法・行政組織法としての性格が強い。また、神道に、儒教・仏教の思想が入っている
本文内容見本
十七条憲法 書き下し 現代語訳
一に曰く、和(やはらぎ)をもって貴(たつと)しと為す。忤(さか)ふることなきを宗(むね)とせよ。人、皆な党(たむら)あり。また達(さと)れる者は少し。これをもって、あるいは君父(きみかそ)に順(まつろ)はず、ながら(また)隣里(さととなり)に違(たが)ふ。然れども上和(やは)らぎ、下睦(むつ)びて諧(ととの)へば、事を論(あげつ)らはむに、則ち理(ことわり)自ら通(かよ)へり。何事か成らざらむ。
現代語訳
一にいう。和をなによりも大切なものとし、いさかいをおこさぬことを根本としなさい。人はグループをつくりたがり、悟りきった人格者は少ない。それだから、君主や父親のいうことにしたがわなかったり、近隣の人たちともうまくいかない。しかし上の者も下の者も協調・親睦(しんぼく)の気持ちをもって論議するなら、おのずからものごとの道理にかない、どんなことも成就(じょうじゅ)するものだ。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.42 聖徳太子十七条憲法Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 42 | 1 | 聖徳太子 | 十七条憲法 内容 | 205 | 小 |
| 42 | 2 | 聖徳太子 | 十七条憲法 書き下し 現代語訳 | 5750 | 中 |
| 42 | 3 | 聖徳太子 | 十七条憲法 原文 | 1149 | 小 |
名作速読朗読文庫vol.43 大和物語 Professional版
名作速読朗読文庫vol.43 大和物語 Professional版
大和物語(原文)
作者未詳
内容
大和物語 とは、平安時代当時の貴族社会の和歌を中心とした歌物語物語である。
当時の貴族社会の和歌を中心とした歌物語で、平安時代前期『伊勢物語』の成立後、天暦5年(951年)頃までに執筆されたと思われる。 登場する人物たちの名称は実名、官名、女房名であり、具体的にある固定の人物を指していることが多い。 通常では、内容は173段に区切られる。約300首の和歌が含まれているが、『伊勢物語』とは異なり統一的な主人公はおらず、各段ごとに和歌 にまつわる説話や、当時の天皇・貴族・僧ら実在の人物による歌語りが連なっている。
第140段までの前半は(物語成立の)近年に詠まれた歌を核として、皇族貴族たちがその由来を語る歌語りであり、141段からの後半は、悲恋や 離別、再会など人の出会いと歌を通した古い民間伝説が語られている 二人の男から求婚された乙女が生田川に身を投げる「生田川伝説」(147段)、 「姥捨山伝説」(156段)などである。また『伊勢物語』にあらわれる「筒井筒」と同じ話が『大和物語』にも出てくるなど、『伊勢物語』の影響は色濃い。
本文内容見本
群書類従巻第三百八 物語部二 大和物語 上
【一】
亭子のみかといまはおりい給いなんとするころ広記殿のかへに伊勢のこのかきつけける
別るれとあいもおしまぬ百敷をみさらんことのなにかかなしき
とありけれはみかと御らんしてそのかたはらにかきつけさせたもうける
身一つにあらぬはかりをおしなへて行めくりてもなにか見さらん
となむありける
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.43 大和物語 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文章量 | |
| 43 | 1 | 作者未詳 | 大和物語 内容 | 556 | 小 |
| 43 | 2 | 作者未詳 | 大和物語第001段 - 第020段 | 3302 | 小 |
| 43 | 3 | 作者未詳 | 大和物語第021段 - 第040段 | 2259 | 小 |
| 43 | 4 | 作者未詳 | 大和物語第041段 - 第060段 | 2478 | 小 |
| 43 | 5 | 作者未詳 | 大和物語第061段 - 第080段 | 2979 | 小 |
| 43 | 6 | 作者未詳 | 大和物語第081段 - 第100段 | 3163 | 小 |
| 43 | 7 | 作者未詳 | 大和物語第101段 - 第120段 | 1871 | 小 |
| 43 | 8 | 作者未詳 | 大和物語第121段 - 第140段 | 3459 | 小 |
| 43 | 9 | 作者未詳 | 大和物語第141段 - 第160段 | 11469 | 大 |
| 43 | 10 | 作者未詳 | 大和物語第161段 - 第173段 | 7135 | 中 |
文字数合計 38671
名作速読朗読文庫vol.44 土佐日記 Professional版
土佐日記(原文+一部現代語訳付き)
紀貫之
内容
土佐日記 とは、平安時代に成立した日記文学のひとつである。紀貫之が土佐国から京に帰る最中に起きたでき事を空想も交えた物語であり、成立は承平5年(935年)頃といわれている
紀行文に近い要素をもっており、その後の仮名による表現、特に女流文学の発達に大きな影響を与えた。『蜻蛉日記』、『和泉式部日記』、『紫式部日記』、『更級日記』などの作品にも影響を及ぼした。延長8年 930年 から承平4年 934年にかけての時期、紀貫之は土佐国に国司として赴任していた。その任期を終えて土佐から京へ帰る紀貫之ら一行の55日間の旅路とその話を書き手を女性に見せかけ、ほとんどを仮名で日記風 に 綴った作品である。57首の和歌を含む内容は様々だが、中心となるのは土佐国で亡くなった愛娘を思う心情、そして行程の遅れによる帰京をはやる思いである。ユーモアを多く用いられている
本文内容見本
土佐日記 01(原文)
男もすなる日記というものを、女もしてみむとてするなり。それの年 承平四年 のしはすの二十日あまり一日の、戌の時に門出す。そのよしいささかものにかきつく。ある人県の四年五年はてて例のことども皆しおえて、解由など取りて住むたちより出でて船に乗るべき所へわたる。かれこれ知る知らぬおくりす。年ごろよく具しつる人々なむわかれ難く思いてその日頻にとかくしつつののしるうちに夜更けぬ。
廿二日、和泉の国までとたひらかにねがいたつ。藤原の言実船路なれど馬の餞す。上中下ながら酔い過ぎていと怪しくしほ海のほとりにてあざれあへり。
廿三日、八木の康教という人あり。この人国に必ずしもいいつかう者にもあらざるなり。これぞ正しきようにて馬の餞したる。かみがらにやあらむ、国人の心の常として今はとて見えざなるを心あるものは恥じずき(ぞイ)なむきける。これは物によりて誉むるにしもあらず。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.44 土佐日記 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 44 | 1 | 紀貫之 | 土佐日記 内容 | 421 | 小 |
| 44 | 2 | 紀貫之 | 土佐日記 01原文 | 1469 | 小 |
| 44 | 3 | 紀貫之 | 土佐日記 02原文 | 2486 | 小 |
| 44 | 4 | 紀貫之 | 土佐日記 03原文 | 1313 | 小 |
| 44 | 5 | 紀貫之 | 土佐日記 04原文 | 2344 | 小 |
| 44 | 6 | 紀貫之 | 土佐日記 05原文 | 1731 | 小 |
| 44 | 7 | 紀貫之 | 土佐日記 06原文 | 1426 | 小 |
| 44 | 8 | 紀貫之 | 土佐日記 07原文 | 1035 | 小 |
| 44 | 8 | 紀貫之 | 土佐日記 01門 出 現代語訳 | 777 | 小 |
| 44 | 9 | 紀貫之 | 土佐日記 02送別の宴 現代語訳 | 866 | 小 |
| 44 | 10 | 紀貫之 | 土佐日記 03船 出 現代語訳 | 1538 | 小 |
| 44 | 11 | 紀貫之 | 土佐日記 04元 日 現代語訳 | 497 | 小 |
| 44 | 12 | 紀貫之 | 土佐日記 05大湊の泊 現代語訳 | 2022 | 小 |
| 44 | 13 | 紀貫之 | 土佐日記 06宇多の松原 現代語訳 | 1854 | 小 |
| 44 | 14 | 紀貫之 | 土佐日記 07羽 根 現代語訳 | 1041 | 小 |
| 44 | 15 | 紀貫之 | 土佐日記 08暁月夜 現代語訳 | 702 | 小 |
| 44 | 16 | 紀貫之 | 土佐日記 09安倍仲磨の歌 現代語訳 | 1328 | 小 |
| 44 | 17 | 紀貫之 | 土佐日記 10かしらの雪 現代語訳 | 984 | 小 |
| 44 | 18 | 紀貫之 | 土佐日記 11海賊の恐れ 現代語訳 | 956 | 小 |
| 44 | 19 | 紀貫之 | 土佐日記 12子の日の歌 現代語訳 | 910 | 小 |
| 44 | 20 | 紀貫之 | 土佐日記 13阿波の水門 現代語訳 | 536 | 小 |
| 44 | 21 | 紀貫之 | 土佐日記 14黒崎の松 現代語訳 | 872 | 小 |
| 44 | 22 | 紀貫之 | 土佐日記 15忘れ貝 現代語訳 | 838 | 小 |
| 44 | 23 | 紀貫之 | 土佐日記 16住 吉 現代語訳 | 1363 | 小 |
| 44 | 24 | 紀貫之 | 土佐日記 17淀 川 現代語訳 | 1259 | 小 |
| 44 | 25 | 紀貫之 | 土佐日記 18渚の院 現代語訳 | 878 | 小 |
| 44 | 26 | 紀貫之 | 土佐日記 19帰 京 現代語訳 | 2112 | 小 |
文字数合計 33558
名作速読朗読文庫vol.45 枕草子-原文 Professional版
枕草子(原文+主要部現代語訳付き)
清少納言
内容
枕草子(まくらのそうし)とは、平安時代中期に中宮定子に仕えた女房清少納言により執筆されたと伝わる随筆である。
平仮名を中心として書かれ、軽妙な筆致の短編が多いが、中関白家の没落と清少納言の仕えた中宮定子の身 にふりかかった不幸を反映して、感傷が交じった心情の吐露もある。作者の洗練されたセンスと、事物への 鋭い観察眼が、『源氏物語』の心情的な「もののあはれ」に対し、知性的な「おかし」の美世界を現出させている。 全般に 簡潔な文で書かれ、一段の長さも短く、 読みやすい内容である。
本文内容見本
(一段) 原文
春は曙(あけぼの)。ようよう白くなりゆく山際(やまぎわ)、すこしあかりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。 夏は夜。月の頃はさらなり、闇もなお、蛍(ほたる)飛びちがいたる。雨など降るも、おかし。 秋は 夕暮(ゆうぐれ)。夕日のさして山端(やまぎわ)いと近くなりたるに、烏(からす)の寝所(ねどころ)へ行くとて、三つ四つ二つなど、飛び行くさえあはれなり。まして雁(かり)などのつらねたるが、いと小さく見ゆる、いとを かし。日入(ひい)りはてて、風の音(おと)、虫の音(ね)など。(いとあわれなり。) 冬はつとめて。雪の降りたるは、いうべきにもあらず。霜などのいと白きも、またさらでも いと寒きに、火など急ぎおこして、炭(すみ) 持てわたるも、いとっきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、炭櫃(すびつ)・火桶(ひおけ)の火も、白き灰がちになりぬるは わろし。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.45 枕草子-原文 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 45 | 1 | 清少納言 | 枕草子 内容 | 363 | 小 |
| 45 | 2 | 清少納言 | 枕草子001段 - 030段 原文 | 15079 | 大 |
| 45 | 3 | 清少納言 | 枕草子031段 - 060段 原文 | 13227 | 大 |
| 45 | 4 | 清少納言 | 枕草子061段 - 090段 原文 | 11117 | 大 |
| 45 | 5 | 清少納言 | 枕草子091段 - 120段 原文 | 21444 | 大 |
| 45 | 6 | 清少納言 | 枕草子121段 - 150段 原文 | 15629 | 大 |
| 45 | 7 | 清少納言 | 枕草子151段 - 180段 原文 | 9310 | 大 |
| 45 | 8 | 清少納言 | 枕草子181段 - 210段 原文 | 8266 | 大 |
| 45 | 9 | 清少納言 | 枕草子211段 - 240段 原文 | 6124 | 大 |
| 45 | 10 | 清少納言 | 枕草子241段 - 270段 原文 | 13358 | 大 |
| 45 | 11 | 清少納言 | 枕草子271段 - 300段 原文 | 8471 | 大 |
| 45 | 12 | 清少納言 | 枕草子301段 - 323段 原文 | 7119 | 大 |
文字数合計 129507
名作速読朗読文庫vol.46 竹取物語 Professional版
竹取物語(原文+現代語訳付き)
(作者不詳)
竹取物語(たけとりものがたり)は、日本の物語。成立年、作者ともに未詳。『竹取物語』は通称で、『竹取翁の物語』とも『かぐや姫の物語』とも呼ばれている。
本文内容見本
かぐや姫誕生
今は昔、竹取の翁(おきな)という者ありけり。野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使いけり。名をば、さぬきの造(みやつこ)となむ言いける。その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。あやしがりて寄りて見るに、筒の中光りたり。それを見れば、三寸ばかりなる人、いとうつくしうていたり。翁言うよう、「我、朝ごと夕ごとに見る竹の中におはするにて、知りぬ。子となり給うべき人なめり」とて、手にうち入れて家へ持ちて来ぬ。妻(め)の嫗(おうな)に預けて養わす。うつくしきことかぎりなし。いと幼ければ籠(こ)に入れて養う。
現代語訳
今となっては昔のこと、竹取りの翁という者がいた。野山に入って竹を取っては、さまざまなことに使っていた。名前はさぬきの造といった。彼が取っている竹の中で、根元が光る竹が一本あった。不思議に思って近寄ってみると、竹の筒の中から光っている。その筒の中を見ると、三寸くらいの人がたいそうかわいらしい様子で坐っている。じいさんが言うには、「私が毎朝毎晩見る竹の中にいらっしゃるので分かった。きっと私の子になりなさるはずの人のようだ」と思い、手のひらに入れて家へ持ち帰った。彼の妻であるばあさんに預けて育てた。かわいらしいことこの上ない。たいそう小さいので、かごに入れて育てた。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.46 竹取物語 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 46 | 1 | 和田万吉 | 竹取物語 内容 | 68 | 小 |
| 46 | 2 | 和田万吉 | ○かぐや姫誕生 | 486 | 小 |
| 46 | 3 | 和田万吉 | ○かぐや姫の成長 | 937 | 小 |
| 46 | 4 | 和田万吉 | ○貴公子たち求婚 | 645 | 小 |
| 46 | 5 | 和田万吉 | ○石作り皇子 | 1617 | 小 |
| 46 | 6 | 和田万吉 | ○庫持皇子 | 923 | 小 |
| 46 | 7 | 和田万吉 | ○帝の求婚 | 479 | 小 |
| 46 | 8 | 和田万吉 | ○かぐや姫告白 | 655 | 小 |
| 46 | 9 | 和田万吉 | ○月からの使者 | 564 | 小 |
| 46 | 10 | 和田万吉 | ○かぐや姫昇天 | 407 | 小 |
| 46 | 11 | 和田万吉 | ○不死の薬 | 932 | 小 |
| 46 | 12 | 和田万吉 | 竹取物語 全編 | 7713 | 大 |
文字数合計 15426
名作速読朗読文庫vol.47 新古今集 Professional版
新古今和歌集 (原文)
藤原定家ほか
内容
新古今和歌集 とは、鎌倉時代初期に編纂された勅選和歌集で全二十巻ある
『新古今和歌集』は後鳥羽院の命によって編纂された勅選和歌集である。
編纂の方針は「先ず万葉集の中を抽き、更に七代集の外を拾う」(真名序)、すなわち『万葉集』とそれまでの勅
選和歌集に採られなかった和歌より選ぶとした。
構成 『古今和歌集』に倣い、「真名序」と「仮名序」の二つの序文がある。
【定家八代抄にもれた主な名歌】
山ふかみ春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水(式子内親王)
なごの海の霞の間よりながむれば入日をあらふ沖つ白波(実定)
見わたせば山本かすむ水無瀬川夕べは秋となにおもひけん(後鳥羽院)
春の夜の夢の浮橋とだえして峯に別るる横雲の空(定家)
樗(あふち)咲くそともの木陰露おちて五月雨はるる風わたるなり(藤原忠良)
待つ宵にふけゆく鐘の声きけばあかぬ別れの鳥は物かは(小侍従)
心なき身にもあはれは知られけり鴫たつ沢の秋の夕暮(西行)
見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮(定家)
本文内容見本
巻第一(春上)34首
春たつ心をよみ侍りける 摂政太政大臣
0001 みよし野は山もかすみて白雪のふりにし里に春は来にけり(0004)
春のはじめの歌 太上天皇
0002 ほのぼのと春こそ空に来にけらし天の香久山霞たなびく(0005)
堀河院御時、百首歌奉りけるに、残りの雪の心をよみ侍りける
権中納言国信
0010 春日野の下萌えわたる草の上につれなくみゆる春のあは雪(0022)
題しらず 山辺赤人
0011 あすからは若菜つまむと標しめし野に昨日もけふも雪は降りつつ(0014)
百首歌奉りし時 藤原家隆朝臣
0017 谷川のうち出づる浪も声たてつ鴬さそへ春の山風(0029)
和歌所にて、関路鴬ということを 太上天皇
0018 鴬の鳴けどもいまだふる雪に杉の葉白き逢坂の山(0032)
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.47 新古今集 Professional版
| vol | 件数 | 作者 | 作品 | 文字数 | 文章量 |
| 47 | 1 | 藤原定家ほか | 新古今和歌集 内容 | 572 | 小 |
| 47 | 2 | 藤原定家ほか | 巻第一 春歌 上 | 1826 | 小 |
| 47 | 3 | 藤原定家ほか | 巻第二 春歌 下 | 1817 | 小 |
| 47 | 4 | 藤原定家ほか | 巻第三 夏歌 | 1014 | 小 |
| 47 | 5 | 藤原定家ほか | 巻第四 秋歌 上 | 1867 | 小 |
| 47 | 6 | 藤原定家ほか | 巻第五 秋歌 下 | 2227 | 小 |
| 47 | 7 | 藤原定家ほか | 巻第六 冬歌 | 2235 | 小 |
| 47 | 8 | 藤原定家ほか | 巻第七 賀歌 | 735 | 小 |
| 47 | 9 | 藤原定家ほか | 巻第八 哀傷歌 | 1683 | 小 |
| 47 | 10 | 藤原定家ほか | 巻第九 離別歌 | 378 | 小 |
| 47 | 11 | 藤原定家ほか | 巻第十 羇旅歌 | 1508 | 小 |
| 47 | 12 | 藤原定家ほか | 巻第十一 恋歌 一 | 1909 | 小 |
| 47 | 13 | 藤原定家ほか | 巻第十二 恋歌 二 | 1356 | 小 |
| 47 | 14 | 藤原定家ほか | 巻第十三 恋歌 三 | 1237 | 小 |
| 47 | 15 | 藤原定家ほか | 巻第十四 恋歌 四 | 1681 | 小 |
| 47 | 16 | 藤原定家ほか | 巻第十五 恋歌 五 | 1568 | 小 |
| 47 | 17 | 藤原定家ほか | 巻第十六 雑歌 上 | 1581 | 小 |
| 47 | 18 | 藤原定家ほか | 巻第十七 雑歌 中 | 1399 | 小 |
| 47 | 19 | 藤原定家ほか | 巻第十八 雑歌 下 | 2413 | 小 |
| 47 | 20 | 藤原定家ほか | 巻第十九 神祇歌 | 747 | 小 |
| 47 | 21 | 藤原定家ほか | 巻第二十 釈教歌 | 1251 | 小 |
文字数合計 31004
名作速読朗読文庫vol.48 和泉式部物語 Professional版
和泉式部日記(原文)
和泉式部
内容
『和泉式部日記』(いずみしきぶにっき)は和泉式部によって記された日記であり、女流日記文学の代表的作品である。
長保5年(1003年)4月?寛弘元年(1004年)1月までの数ヶ月間の出来事が書かれている。恋人冷泉帝第三皇子弾正宮為尊親王が前年長保4年に薨じ、また為尊親王との恋のため父親にも勘当され、さらに夫橘道貞との関係も冷めたものとなって嘆きつつ追憶の日々を過ごしていた和泉式部のもとに、為尊親王の弟冷泉帝第四皇子帥宮敦道親王の消息の便りが届く。その後帥宮と和歌や手紙などを取り交わし、また数度の訪問を受けるうちにお互いを深く愛する関係となり、最終的に和泉式部は帥宮邸に迎えられる。この間の和歌の取り交わしと、この恋愛に関する和泉式部のありのままの心情描写が本作品の大きな特色である。
本文内容見本
和泉式部日記01(原文)
夢よりもはかなきよの中をなげきつつあかしくらすほどに、はかなくて四月にもなりぬれば、木の下くらがりもていく。はしのかたをながむれば、ついひぢのうえの草のあをやかなるをも、ひとはことにめとどめぬを、哀にながむるほどに、ちかきすいがいのもとにひとのけわひすれば、誰にかとおもうほどに、さしいでたるをみれば、故宮にさぶらひしことねりわらわなりけり。あはれに物をおもうほどにきたれば、「などかいとひさしうみえざりつる。遠ざかるむかしの名残にはとおもうを」など いはすれば、 「そのこととさぶらはでは、なれなれしきようにやとっつましうさぶらふうちに、日比山寺にまかりありき侍つるになむ。いとたよりなくつれづれに侍りしかば、御かわりにみまいらせんとてそつの宮になん参りて侍し」とかたれば、「いとよき事にぞあなれ。その宮はいとけぢこうおはしますなるは、むかしのようには、えしもあらじ」などいえば、「しかおはしませど、いとけぢこうおはしまして、『まいるや』ととはせ給う。『参り侍る』と申侍つれば、『これまいらせよ。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.48 和泉式部物語 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 45 | 1 | 和泉式部 | 和泉式部日記内容 | 438 | 小 |
| 45 | 2 | 和泉式部 | 和泉式部日記01 | 1609 | 小 |
| 45 | 3 | 和泉式部 | 和泉式部日記02 | 1244 | 小 |
| 45 | 4 | 和泉式部 | 和泉式部日記03 | 1051 | 小 |
| 45 | 5 | 和泉式部 | 和泉式部日記04 | 1883 | 小 |
| 45 | 6 | 和泉式部 | 和泉式部日記05 | 1396 | 小 |
| 45 | 7 | 和泉式部 | 和泉式部日記06 | 839 | 小 |
| 45 | 8 | 和泉式部 | 和泉式部日記07 | 748 | 小 |
| 45 | 9 | 和泉式部 | 和泉式部日記08 | 2116 | 小 |
| 45 | 10 | 和泉式部 | 和泉式部日記09 | 3334 | 中 |
| 45 | 11 | 和泉式部 | 和泉式部日記10 | 3214 | 中 |
| 45 | 12 | 和泉式部 | 和泉式部日記11 | 4424 | 中 |
文字数合計 22296
名作速読朗読文庫vol.49 保元物語 Professional版
保元物語(原文)
作者不詳
内容
保元物語(ほうげんものがたり)は 保元元年(1156年)に起こった保元の乱を中心に描いた軍記物語である。
保元元年(1156年)に起こった保元の乱を中心に、その前後の事情を和漢混交文で描く。鳥羽法皇の崇徳院への 譲位問題より始まり、鳥羽法皇が崩御したのをきっかけに崇徳院が挙兵。崇徳院と後白河天皇との皇位継承争いを軸に 、 藤原忠通、藤原頼長の摂関家の対立、源義朝と源為義の源氏の対立、平清盛と平忠正との平家の対立が加わり、 崇徳側の敗退、以降の平治の乱、治承・寿永の内乱の予兆までが書かれている。 源為朝の活躍が主となっていて、また為朝の父の源為義をはじめ、敗者となった崇徳・頼長らに同情的である ことが本作品の主題ともいえる。 この『保元物語』に『平治物語』『平家物語』『承久記』を合わせた4作品は「四部の合戦状」といわれている
本文内容見本
保元物語
巻之一
『後白河院御即位の事』
爰に鳥羽の禅定法皇と申し奉るは、天照大神四十六世の御末、神武天皇より七十四代の御門也。堀川天皇第一の 皇子、御母は贈皇太后宮藤茨子、閑院の大納言実季卿の御むすめなり。康和五年正月十六日に御誕生、同年の八月 十六日、皇太子にたたせ給う。嘉永二年七月十九日、堀川院かくれさせ給いしかば、太子五歳にて践祚あり。御在位十六ケ年が間、海内静にして天下おだやか也。寒暑も節をあやまたず、民屋もまことにゆたか也。保安四年正月 廿八日、御年廿一にして御位をのがれて、第一の宮崇徳院にゆずり奉り給。大治四年七月七日、白河院かくれさせ 給てより後は、鳥羽院天下の事をしろしめして、まつりごとをおこない給う。忠ある者を賞じおはします事、聖代・聖主の先規にたがはず、罪ある者をもなだめ給事、大慈・大悲の本誓に叶いまします。されば恩光にてらされ、 徳沢にうるおいて、国も富民もやすかりき。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.49 保元物語 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 49 | 1 | 作者不詳 | 保元物語 内容 | 846 | 小 |
| 49 | 2 | 作者不詳 | 保元物語 序 序 | 391 | 小 |
| 49 | 3 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 後白河院御即位の事 | 1966 | 小 |
| 49 | 4 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 法皇熊野御参詣并びに御託宣の事 | 863 | 小 |
| 49 | 5 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 法皇崩御の事 | 2227 | 小 |
| 49 | 6 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 新院御謀反思し召し立つ事 | 1219 | 小 |
| 49 | 7 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 官軍方方手分けの事 | 394 | 小 |
| 49 | 8 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 親治等生捕らるる事 | 1759 | 小 |
| 49 | 9 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 新院御謀反露顕并びに調伏の事付けたり内府意見の事 | 1720 | 小 |
| 49 | 10 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 新院為義を召さるる事付けたり鵜丸の事 | 1722 | 小 |
| 49 | 11 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 左大臣殿上洛の事付けたり著到の事 | 806 | 小 |
| 49 | 12 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 官軍召し集めらるる事 | 384 | 小 |
| 49 | 13 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 新院御所各門門固めの事付けたり軍評定の事 | 2560 | 小 |
| 49 | 14 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 将軍塚鳴動并びに彗星出ずる事 | 1149 | 小 |
| 49 | 15 | 作者不詳 | 保元物語 巻之一 主上三条保殿に御幸の事付けたり官軍勢汰への事 | 1726 | 小 |
| 49 | 16 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 白河殿へ義朝夜討ちに寄せらるる事 | 3515 | 中 |
| 49 | 17 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 白河殿攻め落す事 | 5375 | 中 |
| 49 | 18 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 新院・左大臣殿落ち給う事 | 818 | 小 |
| 49 | 19 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 新院御出家の事 | 1459 | 小 |
| 49 | 20 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 朝敵の宿所焼き払う事 | 858 | 小 |
| 49 | 21 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 関白殿本官に帰復し給う事付けたり武士に勧賞を行わるる事 | 974 | 小 |
| 49 | 22 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 左府御最後付けたり大相国御嘆きの事 | 2634 | 小 |
| 49 | 23 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 勅を奉じて重成新院を守護し奉る事 | 261 | 小 |
| 49 | 24 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 謀反人各召し捕らるる事 | 807 | 小 |
| 49 | 25 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 重仁親王の御事 | 244 | 小 |
| 49 | 26 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 為義降参の事 | 2705 | 小 |
| 49 | 27 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 忠正・家広等誅せらるる事 | 549 | 小 |
| 49 | 28 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 為義最後の事 | 2998 | 小 |
| 49 | 29 | 作者不詳 | 保元物語 巻之二 義朝の弟ども誅せらるる事 | 713 | 小 |
| 49 | 30 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 義朝幼少の弟ことごとく失わるる事 | 3549 | 中 |
| 49 | 31 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 為義の北の方身を投げ給う事 | 2181 | 小 |
| 49 | 32 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 左大臣殿の御死骸実検の事 | 939 | 小 |
| 49 | 33 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 新院賛州に御遷幸の事并びに重仁親王の御事 | 3574 | 中 |
| 49 | 34 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 無塩君の事 | 1524 | 小 |
| 49 | 35 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 左府の君達并びに謀反人各遠流の事 | 1939 | 小 |
| 49 | 36 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 大相国御上洛の事 | 488 | 小 |
| 49 | 37 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 新院御経沈めの事付けたり崩御の事 | 2197 | 小 |
| 49 | 38 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 為朝生捕り遠流に処せらるる事 | 1079 | 小 |
| 49 | 39 | 作者不詳 | 保元物語 巻之三 為朝鬼が島に渡る事并びに最後の事 | 4019 | 中 |
文字数合計 65131
名作速読朗読文庫vol.50 方丈記 Professional版
方丈記(原文)
鴨長明
内容
方丈記(ほうじょうき)は、鴨長明(かものちょうめい)による鎌倉時代の随筆で、日本中世文学の代表的な随筆である 約100年後の『徒然草』、『枕草子』とあわせ「日本三大随筆」とも呼ばれている。
長明は晩年、京の郊外・日野山に一丈四方(方丈)の狭い庵でくらした。 庵内から当時の世間を観察し、書き記した記録であることから「方丈記」と自ら名付けた。 漢字と仮名の混ざった和漢混交文で書かれたものとしては、最初の優れた文芸作品であり、 漢文の語法、歌語、仏教用語を織り交ぜている。無常観の文学とも言われ、乱世をいかに生きるかという自伝的な人生論とされる。 「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ 消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」の書き出しで移り行くもののはかなさと、同時代のわざわいについて書かれ、後半には自らの草庵の生活が語られている
本文内容見本
方丈記 原文01
鴨長明
行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとどまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし。玉しきの都の中にむねをならべいらかをあらそへる、たかき いやしき人のすまいは、代々を経て尽きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家はまれなり。あるいはこぞ破れてことしは造り、あるは大家ほろびて小家となる。住む人もこれにおなじ。所もかわらず、人も 多かれど、いにしえ見し人は、二三十人が中に、わずかにひとりふたりなり。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.50 方丈記 Professional版
| vol | 件数 | 作者名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 49 | 1 | 鴨 長明 | 方丈記 内容 | 409 | 小 |
| 49 | 2 | 鴨 長明 | 方丈記原文01 | 2371 | 小 |
| 49 | 3 | 鴨 長明 | 方丈記原文02 | 1767 | 小 |
| 49 | 4 | 鴨 長明 | 方丈記原文03 | 2526 | 小 |
| 49 | 5 | 鴨 長明 | 方丈記原文04 | 2750 | 小 |
| 49 | 5 | 鴨 長明 | 方丈記原文全編通し | 9823 | 大 |
文字数合計 19646
名作速読朗読文庫vol.51 山家和歌集 Professional版
山家和歌集(原文)
西行法師
内容
山家和歌集は、平安末期の 西行法師の歌集で、成立年は治承・寿永の乱(源平合戦)のころの作品といわれている。 俊成・良経・慈円・定家・家隆ら5人の家集とともに六家集の一に数えられている 自然と人生を詠い 無常の世をいかに生きるかを問いかけている。
歌数は約1560首だが、増補本ではそのほかに300首余を持つ。諸国を渡り歩いた 西行なので、叙情性の高い花鳥風月の歌や、闊達な人生観のものが多い
構成内容は上巻には四季の歌を、中巻は恋と雑、下巻には恋百十首・雪月花などの十題百首や、離別・羇旅・哀傷・釈教・神祇などの雑の歌が収められている。
本文内容見本
山家集 巻上:春
立春の朝よみける
年くれぬ春くべしとは思いねにまさしく見えてかなふ初夢
山のはのかすむけしきにしるきかな今朝よりやさは春の曙
春たつと思いもあえぬ朝戸出にいつしかかすむ音羽山かな
たちかわる春をしれとも見せがほに年を隔つる霞なりけり
とけそむるはつ若水のけしきにて春立つことのくまれぬる哉
家々に春を翫ぶということを
門ごとにたつる小松にかざされて宿てふやどに春は来にけり
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.51 山家和歌集 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 51 | 1 | 西行法師 | 山家和歌集 内容 | 330 | 小 |
| 51 | 2 | 西行法師 | 山家集 巻上:春 | 5928 | 中 |
| 51 | 3 | 西行法師 | 山家集 巻上:夏 | 2737 | 小 |
| 51 | 4 | 西行法師 | 山家集 巻上:秋 | 7848 | 大 |
| 51 | 5 | 西行法師 | 山家集 巻上:冬 | 3185 | 中 |
| 51 | 6 | 西行法師 | 山家集 巻中:恋 | 3847 | 中 |
| 51 | 7 | 西行法師 | 山家集 巻中:雑 | 13399 | 大 |
| 51 | 8 | 西行法師 | 山家集 巻下 | 18220 | 大 |
| 51 | 9 | 西行法師 | 山家集 巻下:百首 | 2822 | 小 |
文字数合計 58316
名作速読朗読文庫vol.91 義経記 Professional版
義経記(ぎけいき) (原文)
作者不詳
内容
義経記(ぎけいき)は、源義経とその主従を中心に書いた軍記物語で、南北朝時代から室町時代初期に成立したといわれている。能や歌舞伎、人形浄瑠璃など、後世の多くの文学作品に影響を与え、今日の義経やその周辺の人物のイメージの多くは『義経記』によるものである
義経及びその主従などの登場人物たちがよく感情を表し、生き生きと書かれている。 分類は軍記物語ではあるが、『平家物語』のように華々しい合戦の時期に重点が置かれているのではなく、義経の幼少期・出世・没落の時期に重点が置かれている。
本文内容見本
義経記巻第一(だいいち)
義朝(よしとも)都落(みやこおち)の事(こと)
本朝(ほんちょう)の昔(むかし)を尋(たづ)ぬれば、田村(たむら)、利仁(としひと)、将門(まさかど)、純友(すみとも)、保昌(ほうしょう)、頼光(らいくわう)、漢(かん)の樊■(はんくわい)、張良(ちょうりょう)は武勇(ぶゆう)と雖(いえど)も名をのみ聞(き)きて目(め)には見(み)ず。目(ま)のあたりに芸(げい)を世にほどこし、万事の、目(め)を驚(おどろ)かし給(たま)いしは、下野(しもつけ)の左馬頭(さまのかみ)義朝(よしとも)の末(すえ)の子、九郎義経(よしつね)とて、我(わ)が朝(ちょう)にならびなき名将軍(めいしょうぐん)にておはしけり。父(ちち)義朝(よしとも)は平治(へいぢ)元年+十二月+二十七日に衛門督(えもんのかみ)藤原(ふじはらの)信頼卿(のぶよりのきょう)に与(くみ)して、京の軍(いくさ)に打(う)ち負(ま)けぬ。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.91 義経記 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 91 | 1 | 作者不詳 | 義経記巻第一 義経記 内容 | 691 | 小 |
| 91 | 2 | 作者不詳 | 義経記巻第一 義朝(よしとも)都落(みやこおち)の事(こと) | 1274 | 小 |
| 91 | 3 | 作者不詳 | 義経記巻第一 常盤(ときは)都落(みやこおち)の事(こと) | 2020 | 小 |
| 91 | 4 | 作者不詳 | 義経記巻第一 牛若(うしわか)鞍馬入(くらまいり)の事(こと) | 1673 | 小 |
| 91 | 5 | 作者不詳 | 義経記巻第一 聖門(しようもん)坊(ばう)の事(こと) | 2738 | 小 |
| 91 | 6 | 作者不詳 | 義経記巻第一 牛若(うしわか)貴船詣(きゅうねまうで)の事(こと) | 2655 | 小 |
| 91 | 7 | 作者不詳 | 義経記巻第一 吉次(きちじ)が奥州物語(おうしゅうものがたり)の事(こと) | 5055 | 中 |
| 91 | 8 | 作者不詳 | 義経記巻第一 遮那王殿(しやなわうどの)鞍馬出(くらまいで)の事(こと) | 4211 | 中 |
| 91 | 9 | 作者不詳 | 義経記巻第二 鏡(かがみ)の宿(しゅく)吉次(きちじ)が宿に強盗(ごうとう)の入(い)る事 | 6149 | 大 |
| 91 | 10 | 作者不詳 | 義経記巻第二 遮那王殿(しやなわうどの)元服(げんぶく)の事(こと) | 1771 | 小 |
| 91 | 11 | 作者不詳 | 義経記巻第二 阿濃(あの)の禅師(ぜんじ)に御対面(ごたいめん)の事(こと) | 1786 | 小 |
| 91 | 12 | 作者不詳 | 義経記巻第二 義経(よしつね)陵(みささぎ)が館(たち)焼(や)き給(たま)う事 | 2381 | 小 |
| 91 | 13 | 作者不詳 | 義経記巻第二 伊勢(いせの)三郎はじめて臣下(しんか)になる事 | 9560 | 大 |
| 91 | 14 | 作者不詳 | 義経記巻第二 義経(よしつね)はじめて秀衡(ひでひら)対面(たいめん)の事(こと) | 2347 | 小 |
| 91 | 15 | 作者不詳 | 義経記巻第二 鬼一(おにいち)法眼(ほうがん)の事(こと | 17764 | 大 |
| 92 | 1 | 作者不詳 | 義経記巻第三 義経記 内容 | 643 | 小 |
| 92 | 2 | 作者不詳 | 義経記巻第三 熊野の別当(べっとう)乱行の事(こと) | 4036 | 中 |
| 92 | 3 | 作者不詳 | 義経記巻第三 弁慶(べんけい)生(う)まるる事 | 3762 | 中 |
| 92 | 4 | 作者不詳 | 義経記巻第三 弁慶(べんけい)山門(さんもん)を出(い)づる事 | 11181 | 大 |
| 92 | 5 | 作者不詳 | 義経記巻第三 書写(しょしゃ)炎上(えんじょう)の事(こと) | 8924 | 大 |
| 92 | 6 | 作者不詳 | 義経記巻第三 弁慶(べんけい)洛中(らくちゅう)において人の太刀を取(と)る事 | 3672 | 中 |
| 92 | 7 | 作者不詳 | 義経記巻第三 義経(よしつね)弁慶(べんけい)君臣の契約(けいやく)の事(こと) | 6481 | 大 |
| 92 | 8 | 作者不詳 | 義経記巻第三 頼朝(よりとも)謀反(むほん)の事(こと) | 5010 | 中 |
| 92 | 9 | 作者不詳 | 義経記巻第三 義経(よしつね)謀反(むほん)の事(こと) | 2017 | 小 |
| 92 | 10 | 作者不詳 | 義経記巻第四 頼朝(よりとも) 義経(よしつね) 対面(たいめん) の 事(こと) | 4637 | 中 |
| 92 | 11 | 作者不詳 | 義経記巻第四 義経(よしつね) 平家(へいけ) の 討手(うつて) に 上(のぼ)り 給(たま)う 事 | 4689 | 中 |
| 92 | 12 | 作者不詳 | 義経記巻第四 腰越(こしごえ) の 状 の 事(こと) | 2746 | 小 |
| 92 | 13 | 作者不詳 | 義経記巻第四 土佐坊(とさ ばう) 上洛 の 事(こと) | 22850 | 大 |
| 92 | 14 | 作者不詳 | 義経記巻第四 義経(よしつね) 都落(みやこおち) の 事(こと) | 9102 | 大 |
| 92 | 15 | 作者不詳 | 義経記巻第四 大物(だいもつ) 合戦(かっせん) の 事(こと) | 9852 | 大 |
| 93 | 1 | 作者不詳 | 義経記巻第五 内容 | 697 | 小 |
| 93 | 2 | 作者不詳 | 義経記巻第五 判官(はんかん)吉野山(よしのやま)に入(い)り給(たま)う事 | 5334 | 中 |
| 93 | 3 | 作者不詳 | 義経記巻第五 静(しづか)吉野山(よしのやま)に捨(す)てらるる事 | 5294 | 中 |
| 93 | 4 | 作者不詳 | 義経記巻第五 義経(よしつね)吉野山(よしのやま)を落(お)ち給(たま)う事 | 4729 | 中 |
| 93 | 5 | 作者不詳 | 義経記巻第五 忠信(ただのぶ)吉野(よしの)に止(とど)まる事 | 7804 | 大 |
| 93 | 6 | 作者不詳 | 義経記巻第五 忠信(ただのぶ)吉野山(よしのやま)の合戦(かっせん)の事(こと) | 16218 | 大 |
| 93 | 7 | 作者不詳 | 義経記巻第五 吉野(よしの)法師(ほうし)判官(はんかん)を追(お)ひかけ奉(たてまつ)る事 | 15537 | 大 |
| 93 | 8 | 作者不詳 | 義経記巻第六 忠信(ただのぶ)都(みやこ)へ忍(しの)び上(のぼ)る事 | 4071 | 中 |
| 93 | 9 | 作者不詳 | 義経記巻第六 忠信(ただのぶ)最期(さいご)の事(こと) | 7488 | 大 |
| 93 | 10 | 作者不詳 | 義経記巻第六 忠信(ただのぶ)が首(くび)鎌倉(かまくら)へ下(くだ)る事 | 2291 | 小 |
| 93 | 11 | 作者不詳 | 義経記巻第六 判官(はんかん)南都(なんと)へ忍(しの)び御出(おい)である事 | 6915 | 大 |
| 93 | 12 | 作者不詳 | 義経記巻第六 関東(かんとう)より勧修坊(くわんじゅばう)を召(め)さるる事 | 14783 | 大 |
| 93 | 13 | 作者不詳 | 義経記巻第六 静(しづか)鎌倉(かまくら)へ下(くだ)る事 | 9184 | 大 |
| 93 | 14 | 作者不詳 | 義経記巻第六 静(しづか)若宮(わかみや)八幡宮(はちまんぐう)へ参詣(さんけい)の事(こと) | 16504 | 大 |
| 94 | 1 | 作者不詳 | 義経記巻第七 内容 | 786 | 小 |
| 94 | 2 | 作者不詳 | 義経記巻第七 判官(はんかん)北国落(ほつこくおち)の事(こと) | 13036 | 大 |
| 94 | 3 | 作者不詳 | 義経記巻第七 大津(おほつ)次郎(じらう)の事(こと) | 7893 | 大 |
| 94 | 4 | 作者不詳 | 義経記巻第七 愛発山(あらちやま)の事(こと) | 2172 | 小 |
| 94 | 5 | 作者不詳 | 義経記巻第七 三(みつ)の口(くち)の関(せき)通(とほ)り給(たま)う事 | 10604 | 大 |
| 94 | 6 | 作者不詳 | 義経記巻第七 平泉寺(へいせんじ)御見物(けんぶつ)の事(こと) | 11959 | 大 |
| 94 | 7 | 作者不詳 | 義経記巻第七 如意(によい)の渡(わたり)にて義経(よしつね)を弁慶(べんけい)打(う)ち奉(たてまつ)る事 | 4406 | 中 |
| 94 | 8 | 作者不詳 | 義経記巻第七 直江(なほえ)の津(つ)にて笈(おひ)探(さが)されし事 | 12336 | 大 |
| 94 | 9 | 作者不詳 | 義経記巻第七 亀割山(かめわりやま)にて御産(おさん)の事(こと) | 4661 | 中 |
| 94 | 10 | 作者不詳 | 義経記巻第七 判官(はんかん)平泉(ひらいずみ)へ御著(おんつき)の事(こと) | 1799 | 小 |
| 94 | 11 | 作者不詳 | 義経記巻第八 継信(つぎのぶ)兄弟(きょうだい)御弔(とぶら)ひの事(こと) | 6729 | 大 |
| 94 | 12 | 作者不詳 | 義経記巻第八 秀衡(ひでひら)死去(しきよ)の事(こと) | 2497 | 小 |
| 94 | 13 | 作者不詳 | 義経記巻第八 秀衡(ひでひら)が子供(こども)判官(はんかん)殿(どの)に謀反(むほん)の事(こと) | 5148 | 中 |
| 94 | 14 | 作者不詳 | 義経記巻第八 鈴木(すずき)の三郎重家(しげいへ)高館(たかだち)へ参(まい )る事 | 1304 | 小 |
| 94 | 15 | 作者不詳 | 義経記巻第八 衣河(ころもがは)合戦(かっせん)の事(こと) | 7240 | 大 |
| 94 | 16 | 作者不詳 | 義経記巻第八 判官(はんかん)御自害(ごじがい)の事(こと) | 4463 | 中 |
| 94 | 17 | 作者不詳 | 義経記巻第八 兼房(かねふさ)が最期(さいご)の事(こと) | 1452 | 小 |
| 94 | 18 | 作者不詳 | 義経記巻第八 秀衡(ひでひら)が子供(こども)御追討(ついたう)の事(こと) | 1310 | 小 |
文字数合計 378321
名作速読朗読文庫vol.95 新拾遺和歌集 Professional版
新拾遺和歌集(原文)
二条為明撰
内容
新拾遺和歌集(しんしゅういわかしゅう)は、勅選和歌集で、全20巻。 歌風はわかりやすく、はっきりしている
貞治2年(1363年)、室町幕府第2代将軍足利義詮の執奏により後光厳天皇より綸旨が下った。貞治3年(1364年)4月20日、四季奏覧。10月、為明の死去により頓阿が継いで、12月に成る。部立は、春上下、夏、秋上下、冬、賀、離別、羇旅、哀傷、恋一二三四五、神祇、釈教、雑上中下。雑下に『拾遺和歌集』の組織をまねて雑体歌をのせた。恋および雑の部の歌作者に僧が多い。
本文内容見本
巻第一
春歌上
中納言為藤
春立つ心をよみ侍りける
明け渡る空に志られて久かたの岩戸の関を春や越ゆらむ
法皇御製
春のはじめの御歌
天の戸の明くるを見れば春はきょう霞と共に立つにぞ有ける
前中納言定家
いつしかと外山のかすみ立ち帰りきょうあらたまる春の曙
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.95 新拾遺和歌集 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 95 | 1 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集 内容 | 249 | 小 |
| 95 | 2 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第一 | 3880 | 中 |
| 95 | 3 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第二 | 4503 | 中 |
| 95 | 4 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第三 | 4864 | 中 |
| 95 | 5 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第四 | 4109 | 中 |
| 95 | 6 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第五 | 5879 | 大 |
| 95 | 7 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第六 | 4919 | 中 |
| 95 | 8 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第七 | 2820 | 小 |
| 95 | 9 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第八 | 1204 | 小 |
| 95 | 10 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第九 | 3393 | 中 |
| 95 | 11 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十 | 3870 | 中 |
| 95 | 12 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十一 | 3413 | 中 |
| 95 | 13 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十二 | 3682 | 中 |
| 95 | 14 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十三 | 4482 | 中 |
| 95 | 15 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十四 | 3975 | 中 |
| 95 | 16 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十五 | 2398 | 小 |
| 95 | 17 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十六 | 2467 | 小 |
| 95 | 18 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十七 | 3465 | 中 |
| 95 | 19 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十八 | 7859 | 大 |
| 95 | 20 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第十九 | 6168 | 大 |
| 95 | 21 | 二条為明撰 | 新拾遺和歌集巻第二十 | 2905 | 小 |
文字数合計 80504
名作速読朗読文庫vol.96 水鏡 Professional版
水鏡(原文)
作者未詳
内容
水鏡(みずかがみ)は、歴史物語で、成立は鎌倉時代初期 1195年頃とされている。 国書の『本朝書籍目録』仮名部に「水鏡三巻 中山内府抄」とあることから、作者は中山忠親説 といわれている いわゆる「四鏡」の成立順では3番目に位置する作品で内容的には最も古い時代を扱っている
神武天皇から仁明天皇まで57代の事跡を編年体で述べ、73歳の老婆が、長谷寺に参篭中の夜、修験者が現 れ、不思議な体験を語るのを書き留めたという形になっている。
本文内容見本
水鏡 巻之上01
慎(つつし)むべき年(とし)にて、過ぎにし二月の初午の日、竜覆寺へ詣で侍(はべ)りて、やがてそれより 、初瀬に、たそがれのほどに参(まい)り着きたりしに、年の積もりには、いたく苦しう覚えて、師のもとにしば し休み侍(はべ)りし程に、うちまどろまれにけり。初夜の鐘の声におどろかれて、御前に参(まい)りて通夜し 侍(はべ)りしに、世の中うちしづまる程に、修行者の三十四五などにやなるらんと見えしが、経をいと尊く読む あり。かたはら近くいたれば、「いかなる人のいずこより参(まい)り給(たま)えるぞ。御経などの承(うけた まは)らまほしからむには、尋(たづ)ね奉(たてまつ)らん」というに、この修行者言うよう、
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.96 水鏡 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 96 | 1 | 作者不詳 | 水鏡 内容 | 404 | 小 |
| 96 | 2 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上01 | 2332 | 小 |
| 96 | 3 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上02 | 1730 | 小 |
| 96 | 4 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上03 | 2176 | 小 |
| 96 | 5 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上04 | 2549 | 小 |
| 96 | 6 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上05 | 3058 | 中 |
| 96 | 7 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上06 | 2246 | 小 |
| 96 | 8 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上07 | 1788 | 小 |
| 96 | 9 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上08 | 2127 | 小 |
| 96 | 10 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上09 | 1801 | 小 |
| 96 | 11 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上10 | 2291 | 小 |
| 96 | 12 | 作者不詳 | 水鏡 巻之上11 | 1408 | 小 |
| 96 | 13 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中01 | 2079 | 小 |
| 96 | 14 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中02 | 1992 | 小 |
| 96 | 15 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中03 | 2251 | 小 |
| 96 | 16 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中04 | 2069 | 小 |
| 96 | 17 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中05 | 2343 | 小 |
| 96 | 18 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中06 | 2897 | 小 |
| 96 | 19 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中07 | 5328 | 中 |
| 96 | 20 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中08 | 3402 | 中 |
| 96 | 21 | 作者不詳 | 水鏡 巻之中09 | 1441 | 小 |
| 96 | 22 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下01 | 2358 | 小 |
| 96 | 23 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下02 | 2233 | 小 |
| 96 | 24 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下03 | 1889 | 小 |
| 96 | 25 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下04 | 3272 | 中 |
| 96 | 26 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下05 | 2236 | 小 |
| 96 | 27 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下06 | 2344 | 小 |
| 96 | 28 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下07 | 2227 | 小 |
| 96 | 29 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下08 | 2658 | 小 |
| 96 | 30 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下09 | 2947 | 小 |
| 96 | 31 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下10 | 2665 | 小 |
| 96 | 32 | 作者不詳 | 水鏡 巻之下11 | 2355 | 小 |
文字数合計 74896
名作速読朗読文庫vol.97 曾我物語 Professional版
曽我物語(原文)
作者不詳
内容
曽我物語(そがものがたり)は、鎌倉時代初期に起きた曽我兄弟の仇討ちを題材にした軍記物語である。
建久4年(1193年)5月28日に富士の巻狩りの際に起きたこの事件について公式に書かれた文書は『我妻鏡』以外にない南北朝時代から室町・戦国時代を通じて語り継がれた。 やがて能や人形浄瑠璃として上演されるようになり、これが江戸時代になると歌舞伎化されて「曽我もの」の演目となった。
本文内容見本
曽我物語 上編
巻第一
一 神代(かみよ)のはじまりの事
それ、日域(じちいき)秋津島(あきつしま)は、これ、国常立尊(くにとこたちのみこと)より事おこり、宇比地邇(うひぢに)・須比知邇(すひぢに)、男神(なんしん)・女神(によしん)とあらわれ、伊弉諾(いざなぎ)・ 伊弉冊尊(いざなみのみこと)まで、以上天神七代にわたらせ給(たま)いき。また、天照大神(あまてるおほんかみ)より、彦波瀲武草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあわせずのみこと)まで、以上地神五代にて、多(おお)く の星霜(せいそう)をおくり給(たま)ふ。しかるに、神武(じんむ)天皇(てんのう)と申(もう)し奉(たてまつ)るは、葺不合(ふきあわせず)の尊の皇子(おうじ)にて、一天(いってん)の主(あるじ)、百皇(はくわう) にもはじめとして、天下を治(をさ)め給(たま)いしよりこのかた、国土(こくど)をかたぶけ、万民(ばんみん)のおそるるはかりこと、
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.97 曾我物語 Professional版
| vol | 件数 | 作家 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 97 | 1 | 作者不詳 | 曽我物語 曽我物語 内容 | 749 | 小 |
| 97 | 2 | 作者不詳 | 曽我物語 一 神代(かみよ)のはじまりの事 | 945 | 小 |
| 97 | 3 | 作者不詳 | 曽我物語 二 惟喬(これたか)・惟仁(これひと)の位(くらい)あらそいの事 | 4825 | 中 |
| 97 | 4 | 作者不詳 | 曽我物語 三 伊東(いとう)を調伏(ちょうぶく)する事 | 3504 | 中 |
| 97 | 5 | 作者不詳 | 曽我物語 四 おなじく伊東(いとう)が死(し)する事 | 3102 | 中 |
| 97 | 6 | 作者不詳 | 曽我物語 五 伊東(いとうの)次郎(じろう)と祐経(すけつね)が争論(そうろん)の事 | 5438 | 大 |
| 97 | 7 | 作者不詳 | 曽我物語 六 頼朝伊東(いとう)の館(たち)にまします事 | 2358 | 小 |
| 97 | 8 | 作者不詳 | 曽我物語 七 大見(おほみ)・八幡(やはた)が伊東(いとう)ねらいし事 | 462 | 小 |
| 97 | 9 | 作者不詳 | 曽我物語 八 杵臼(しよきゅう)・程嬰(ていえい)が事 | 5489 | 大 |
| 97 | 10 | 作者不詳 | 曽我物語 九 奥野(おくの)の狩座(かりくら)の事 | 504 | 小 |
| 97 | 11 | 作者不詳 | 曽我物語 十 同じく酒盛りの事 | 3074 | 中 |
| 97 | 12 | 作者不詳 | 曽我物語 十一 おなじく相撲(すまう)の事 | 7924 | 大 |
| 97 | 13 | 作者不詳 | 曽我物語 十二 費長房(ひちょうばう)が事 | 1121 | 小 |
| 97 | 14 | 作者不詳 | 曽我物語 十三 河津(かわずの)三郎(さぶろう)うたれし事 | 4920 | 中 |
| 97 | 15 | 作者不詳 | 曽我物語 十四 伊東(いとう)が出家(しゅっけ)の事 | 837 | 小 |
| 97 | 16 | 作者不詳 | 曽我物語 十五 御房(ばう)がむまるる事 | 935 | 小 |
| 97 | 17 | 作者不詳 | 曽我物語 十六 女房(にょうぼう)、曽我(そが)へうつる事 | 965 | 小 |
| 合計冊数 17 文字数合計 47152 | |||||
名作速読朗読文庫vol.98 徒然草 Professional版
徒然草(原文)
吉田兼好
内容
徒然草(つれづれぐさ)は、吉田兼好(兼好法師)が書いたとされる随筆である。清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方だけ記』と合わせて日本三大随筆の一つと評価されている。
鎌倉時代末期、1330年8月から1331年9月頃にまとめられたといわれている 序段を含めて244段から成る。文体は和漢混交文と、仮名文字が中心の和文が混在している。序段には「つれづれなる ままに」書いたと述べ、その後の各段では、兼好の思索や雑感、逸話を長短様々、順不同に語り、隠者文学の一に位置 づけられる。兼好が歌人、古典学者、能書家などであったことを反映し、内容は多岐にわたり、また、兼好が仁和寺に 居を構えたためか、仁和寺に関する説話が多い。 『徒然草』に記された教訓は町人などにも親しみやすく、身近な古典として愛読され、江戸期の文化に多大な影響を及ぼした。 こうして『徒然草』は古典となり、文学上の位置が確定した。 徒然草が伝える説話のなかには、同時代の事件や人物について知る史料となる記述が散見され、歴史史料としても広く利用 されている。
本文内容見本
・ 第一段
いでや、この世に生れては、願はしかるべきことこそ多かめれ。
帝の御位(おんくらい)はいともかしこし。竹の園生の末葉まで、人間の種ならぬぞやんごとなき。一の人の御有様はさらなり、ただ人も、舎人(とねり)などたまはる際(きわ)は、ゆゆしと見ゆ。その子・孫までは、はふれにたれど、なほなまめかし。それより下つ方は、ほどにつけつつ、時に逢い、したり顔なるも、みづからはいみじと思ふらめど、いと口惜(くちお)し。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.98 徒然草 Professional版
| volの件 | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 98 | 1 | 吉田兼好 | 徒然草 内容 | 598 | 小 |
| 98 | 2 | 吉田兼好 | 徒然草 序 段 | 75 | 小 |
| 98 | 3 | 吉田兼好 | 徒然草 第001段 - 第025段 | 7795 | 大 |
| 98 | 4 | 吉田兼好 | 徒然草 第026段 - 第050段 | 6171 | 中 |
| 98 | 5 | 吉田兼好 | 徒然草 第051段 - 第075段 | 7588 | 大 |
| 98 | 6 | 吉田兼好 | 徒然草 第076段 - 第100段 | 5836 | 中 |
| 98 | 7 | 吉田兼好 | 徒然草 第101段 - 第125段 | 7057 | 大 |
| 98 | 8 | 吉田兼好 | 徒然草 第126段 - 第150段 | 8561 | 大 |
| 98 | 9 | 吉田兼好 | 徒然草 第151段 - 第175段 | 6606 | 中 |
| 98 | 10 | 吉田兼好 | 徒然草 第176段 - 第200段 | 5864 | 中 |
| 98 | 11 | 吉田兼好 | 徒然草 第201段 - 第225段 | 5783 | 中 |
| 98 | 12 | 吉田兼好 | 徒然草 第226段 - 第243段 | 5975 | 中 |
文字数合計 67909
名作速読朗読文庫vol.103 奥の細道 Professional版
おくの細道(原文)
松尾芭蕉
内容
奥の細道は、元禄文化期に活躍した俳人、松尾芭蕉による紀行文で、元禄15年(1702年)刊行された。日本の古典における紀行作品の代表的存在である 作品中に多数の俳句が詠まれている
芭蕉が、ほとんどの旅の中で弟子の河合 曽良を伴い、元禄2年3月27日 1689年5月16日 に江戸深川の採荼庵(さいとあん)を出発し、全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日 をかけ東北・北陸を巡って元禄4年 1691年 に江戸に帰った。「おくのほそ道」では、このうち武蔵から、下野 、岩代、陸前、陸中、陸奥、出羽、越後、越中、加賀、越前を通過して旧暦9月6日美濃大垣を到着するまでが書かれている。
本文内容見本
01 序文(じょぶん)
月日(つきひ)は百代(はくたい)の過客(かかく)にして、行(ゆ)きかふ年もまた旅人(たびびと)なり。
舟の上に生涯(しょうがい)をうかべ、馬の口とらえて老(おい)をむかふるものは、日々(ひび)旅(たび)にして旅(たび)を栖(すみか)とす。
古人(こじん)も多く旅(たび)に死(し)せるあり。
よもいづれの年よりか、片雲(へんうん)の風にさそはれて、漂泊(ひょうはく)の思ひやまず、海浜(かいひん)にさすらへ、去年(こぞ)の秋江上(こうしょう)の破屋(はおく)にくもの古巣(ふるす)をはらひて、やや年も暮(くれ)、春立てる霞(かすみ)の空に白河(しらかわ)の関こえんと、そぞろ神(がみ)の物につきて心をくるはせ、道祖神(どうそじん)のまねきにあひて、取(と)るもの手につかず。
ももひきの破(やぶ)れをつづり、笠(かさ)の緒(お)付(つ)けかえて、三里(さんり)に灸(きゅう)すゆるより、松島の月まず心にかかりて、住(す)める方(かた)は人に譲(ゆず)り、杉風(さんぷう)が別墅(べっしょ)に移(うつ)るに、
草の戸も 住替(すみかわる)る代(よ)ぞ ひなの家
面八句(おもてはちく)を庵(いおり)の柱(はしら)にかけ置(お)く
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.103 奥の細道 Professional版
| vol | 件数 | 作家 | タイトル | 文字数 | 文章量 |
| 103 | 1 | 松尾 芭蕉 | おくの細道 内容 | 990 | 小 |
| 103 | 2 | 松尾 芭蕉 | 序文(じょぶん) | 516 | 小 |
| 103 | 3 | 松尾 芭蕉 | 旅立ち(たびだち) | 344 | 小 |
| 103 | 4 | 松尾 芭蕉 | 草加(そうか) | 365 | 小 |
| 103 | 5 | 松尾 芭蕉 | 室の八島(むろのやしま) | 281 | 小 |
| 103 | 6 | 松尾 芭蕉 | 仏五左衛門(ほとけござえもん) | 348 | 小 |
| 103 | 7 | 松尾 芭蕉 | 日光(にっこう) | 264 | 小 |
| 103 | 8 | 松尾 芭蕉 | 黒髪山(くろかみやま) | 535 | 小 |
| 103 | 9 | 松尾 芭蕉 | 那須(なす) | 472 | 小 |
| 103 | 10 | 松尾 芭蕉 | 黒羽(くろばね) | 514 | 小 |
| 103 | 11 | 松尾 芭蕉 | 雲巌寺(うんがんじ) | 526 | 小 |
| 103 | 12 | 松尾 芭蕉 | 殺生石・遊行柳(せっしょうせき・ゆぎょうやなぎ) | 439 | 小 |
| 103 | 13 | 松尾 芭蕉 | 白河(しらかわ) | 355 | 小 |
| 103 | 14 | 松尾 芭蕉 | 須賀川(すかがわ) | 666 | 小 |
| 103 | 15 | 松尾 芭蕉 | 安積山(あさかやま) | 286 | 小 |
| 103 | 16 | 松尾 芭蕉 | 信夫の里(しのぶのさと) | 257 | 小 |
| 103 | 17 | 松尾 芭蕉 | 佐藤庄司が旧跡(さとうしょうじがきゅうせき) | 510 | 小 |
| 103 | 18 | 松尾 芭蕉 | 飯塚の里(いいづかのさと) | 501 | 小 |
| 103 | 19 | 松尾 芭蕉 | 笠嶋(かさじま) | 308 | 小 |
| 103 | 20 | 松尾 芭蕉 | 武隈の松(たけくまのまつ) | 415 | 小 |
| 103 | 21 | 松尾 芭蕉 | 仙台(せんだい) | 702 | 小 |
| 103 | 22 | 松尾 芭蕉 | 多賀城(たがじょう) | 667 | 小 |
| 103 | 23 | 松尾 芭蕉 | 末の松山・塩竃(すえのまつやま・しおがま) | 506 | 小 |
| 103 | 24 | 松尾 芭蕉 | 塩竃神社(しおがまじんじゃ) | 529 | 小 |
| 103 | 25 | 松尾 芭蕉 | 松島 | 472 | 小 |
| 103 | 26 | 松尾 芭蕉 | 雄島 | 538 | 小 |
| 103 | 27 | 松尾 芭蕉 | 瑞巌寺(ずいがんじ) | 278 | 小 |
| 103 | 28 | 松尾 芭蕉 | 石巻(いしのまき) | 526 | 小 |
| 103 | 29 | 松尾 芭蕉 | 平泉(ひらいずみ) | 853 | 小 |
| 103 | 30 | 松尾 芭蕉 | 尿前の関(しとまえのせき) | 846 | 小 |
| 103 | 31 | 松尾 芭蕉 | 尾花沢(おばねざわ) | 266 | 小 |
| 103 | 32 | 松尾 芭蕉 | 山寺 | 415 | 小 |
| 103 | 33 | 松尾 芭蕉 | 大石田 | 214 | 小 |
| 103 | 34 | 松尾 芭蕉 | 最上川(もがみがわ) | 298 | 小 |
| 103 | 35 | 松尾 芭蕉 | 羽黒山(はぐろさん) | 682 | 小 |
| 103 | 36 | 松尾 芭蕉 | 月山(がっさん) | 932 | 小 |
| 103 | 37 | 松尾 芭蕉 | 鶴岡・酒田(つるおか・さかた) | 237 | 小 |
| 103 | 38 | 松尾 芭蕉 | 象潟(きさがた) | 1120 | 小 |
| 103 | 39 | 松尾 芭蕉 | 越後路(えちごじ) | 303 | 小 |
| 103 | 40 | 松尾 芭蕉 | 市振(いちぶり) | 789 | 小 |
| 103 | 41 | 松尾 芭蕉 | 越中路(えっちゅうじ) | 270 | 小 |
| 103 | 42 | 松尾 芭蕉 | 金沢・小松(かなざわ・こまつ) | 694 | 小 |
| 103 | 43 | 松尾 芭蕉 | 那谷・山中温泉(なた・やまなかおんせん) | 655 | 小 |
| 103 | 44 | 松尾 芭蕉 | 全昌寺 | 599 | 小 |
| 103 | 45 | 松尾 芭蕉 | 汐越の松(しおこしのまつ) | 193 | 小 |
| 103 | 46 | 松尾 芭蕉 | 天龍寺・永平寺(てんりゅうじ・えいへいじ) | 342 | 小 |
| 103 | 47 | 松尾 芭蕉 | 福井(ふくい) | 567 | 小 |
| 103 | 48 | 松尾 芭蕉 | 敦賀(つるが) | 677 | 小 |
| 103 | 49 | 松尾 芭蕉 | 種の浜(いろのはま) | 349 | 小 |
| 103 | 50 | 松尾 芭蕉 | 大垣(おおがき) | 314 | 小 |
文字数合計 24725
名作速読朗読文庫vol.104 小林一茶 Professional版

小林一茶 俳句集(原文+現代語訳)
内容
小林 一茶は江戸時代を代表する俳諧師の一人で本名を小林弥太郎といった。
一茶の句は風雅の味わいがあまりないため、生前は単なる田舎俳諧とされていた。しかし明治時代になり、正岡子規はその強烈な自意識と 鋭い洞察力を高く評価し、松尾芭蕉。与謝蕪村と並ぶ俳人として広く世に知らしめた 正岡子規は「一茶の俳句を評す」の中で「俳句の実質における一茶の特色は、主として滑稽、風刺、慈愛の三点に あり。」と述べている。
代表的な句
雪とけて村いっぱいの子どもかな
大根(だいこ)引き大根で道を教えけり
めでたさも中位(ちゅうくらい)なりおらが春
やせ蛙(がえる)まけるな一茶これにあり
悠然(いうぜん)として山を見る蛙(かえる)かな
雀の子そこのけそこのけお馬が通る
蟻(あり)の道(みち)雲の峰よりつづきけん
やれ打つな蝿(はへ)が手をすり足をする
名月をとってくれろと泣く子かな
これがまあ終(つい)の栖(すみか)か雪五尺
うまそうな雪がふうはりふうはりと
ともかくもあなたまかせの年の暮(くれ)
我ときて遊べや親のない雀
一茶の作った句の数
一茶のつくった句は約22,000句。 芭蕉の約1,000句、蕪村の約3,000句に比べ非常に多い。最も多くの俳句を 残したのは、正岡子規で約24,000句である
本文内容見本
春の句
春めくややぶありて雪ありて雪
この俳句の意味は → 道を行くと藪があり、その根元には残雪がまだ深く残っている。進んで行くとまた藪
があり、また雪が続く。けれども、何となく春めいて、春はもう近いと感じられることである。 この俳句の季語 は → 春めく
雪とけて村いっぱいの子どもかな
この俳句の意味は → 雪国の長い冬がようやく終わり、雪が解け出した。家の中にこもっていた子どもたち
がいっせいに外へ出て遊んでいて、村じゅうが子どもたちでいっぱいだ。 この俳句の季語は → 雪とく
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.104 小林一茶 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 104 | 1 | 小林 一茶 | 小林一茶 俳句集 内容 | 1716 | 小 |
| 104 | 2 | 小林 一茶 | 小林一茶 俳句集 春の句 | 1338 | 小 |
| 104 | 3 | 小林 一茶 | 小林一茶 俳句集 夏の句 | 1319 | 小 |
| 104 | 4 | 小林 一茶 | 小林一茶 俳句集 秋の句 | 1171 | 小 |
| 104 | 5 | 小林 一茶 | 小林一茶 俳句集 冬の句 | 1096 | 小 |
文字数合計 6640
名作速読朗読文庫vol.104 蕪村句集 Professional版
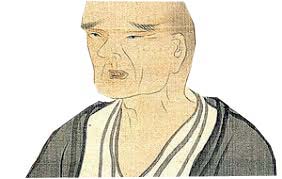
蕪村句集(原文)
与謝 蕪村
内容
蕪村句集は、江戸中期の俳人、画家である与謝 蕪村による作品である 蕪村は松尾芭蕉、小林一茶と並び称される江戸俳諧の巨匠の一人であり、江戸俳諧中興の祖といわれている。
また、俳画の創始者でもある。写実的で絵画的な発句を得意とした。 蕪村に影響された俳人は多いが、特に正岡子規の俳句革新に大きな影響を与えた 。
代表的な俳句
春の海 終日のたりのたり哉
柳散り清水枯れ石処々
鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな
花いばら故郷の路に似たるかな
不二ひとつうづみのこして若葉かな
牡丹散りて打かさなりぬ二三片
夏河を越すうれしさよ手に草履
ゆく春やおもたき琵琶の抱心
易水にねぶか流るる寒かな
月天心貧しき町を通りけり
さみだれや大河を前に家二軒
菜の花や月は東に日は西に
本文内容見本
巻之上 春之部(原文)
ほうらいの山まつりせむ老の春
日の光今朝や鰯のかしらより
三椀の雑煮かゆるや長者ぶり
離落
うぐいすのあちこちとするや小家がち
鴬の声遠き日も暮にけり
うぐいすの鹿相がましき初音哉
鴬を雀歟と見しそれも春
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.104 蕪村句集 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 104 | 1 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 内容 | 557 | 小 |
| 104 | 8 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 後篇 秋之部 | 2696 | 小 |
| 104 | 9 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 後篇 冬之部 | 2969 | 小 |
| 104 | 6 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 後篇 春之部 | 3110 | 中 |
| 104 | 5 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 巻之下 冬之部 | 3122 | 中 |
| 104 | 2 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 巻之上 春之部 | 3351 | 中 |
| 104 | 4 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 巻之下 秋之部 | 3438 | 中 |
| 104 | 7 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 後篇 夏之部 | 3531 | 中 |
| 104 | 3 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 巻之上 夏之部 | 3703 | 中 |
| 104 | 10 | 与謝 蕪村 | 蕪村句集 付録 | 64361 | 大 |
文字数合計 90838
名作速読朗読文庫vol.107 好色一代女 Professional版
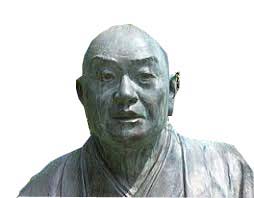
好色一代女(原文)
井原西鶴
内容
好色一代女は、井原西鶴作の浮世草子で、6巻6冊、1686年 貞享3年の刊である。
都に住む当世男が、友人とともに、西嵯峨に行き、草庵の主である老女に会って、生涯の思い出話を聞くという流れである。その内容は、堂上家の姫君に生まれた一代女がその道を踏み外して、悦楽と苦悩とのないまぜになった生活の末に次第次第に転落し、太夫から天神、私娼へと堕ちてゆく。いくたびかその境遇から這い上がろうとして、しかしみずからの性質から、失敗するというものである。
本文内容見本
好色一代女巻一 原文
老女隠家
都にこれ沙汰の女たずねて
むかし物がたりをきけば一代のいたずら
さりとはうき世のしゃれもの
今もまどうつくしき
老女のかくれ家
美女は命を断斧と古人もいえり。心の花散ゆうべの焼木となれるは何れかこれをのがれじ。されども時節の外なる朝の嵐とは。色道におぼれ若死の人こそ愚なれ。その種はつきもせず人の日のはじめ。都のにし嵯峨に行事ありしに。春も今ぞと花の口びるうごく梅津川を渡りし時うつくしげなる当世男の采体しどけなく。色青ざめて恋に貌をせめられ行末頼みすくなく。追付親に跡やるべき人の願い。我万の事に何の不足もなかりき。この川の流れのごとく契水絶ずもあらまほしきといえば。友とせし人驚き我はまた女のなき国もがな。その所に行て閑居を極め惜き身をながらへ。移り替れる世のさまざまを見る事もという。
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.107 好色一代女 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 107 | 1 | 井原 西鶴 | 好色一代女 内容 | 389 | 小 |
| 107 | 2 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻一 老女隠家 | 1972 | 小 |
| 107 | 3 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻一 舞曲遊興 | 1587 | 小 |
| 107 | 4 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻一 国主艶妾 | 2523 | 小 |
| 107 | 5 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻一 淫婦の美形 | 3652 | 中 |
| 107 | 6 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻二 淫婦中位 | 2333 | 小 |
| 107 | 7 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻二 分里数女 | 2631 | 小 |
| 107 | 8 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻二 世間寺大黒 | 1814 | 小 |
| 107 | 9 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻二 諸礼女祐筆 | 1597 | 小 |
| 107 | 10 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻三 町人腰元 | 2405 | 小 |
| 107 | 11 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻三 妖はひの寛活女 | 2537 | 小 |
| 107 | 12 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻三 調譫歌船 | 1731 | 小 |
| 107 | 13 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻三 金紙匕髻結 | 1787 | 小 |
| 107 | 14 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻四 身替長枕 | 1431 | 小 |
| 107 | 15 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻四 墨絵浮気袖 | 2316 | 小 |
| 107 | 16 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻四 屋敷琢渋皮 | 1946 | 小 |
| 107 | 17 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻四 栄耀願男 | 1720 | 小 |
| 107 | 18 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻五 石垣恋崩 | 2154 | 小 |
| 107 | 19 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻五 子哥伝受女 | 1522 | 小 |
| 107 | 20 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻五 美扇恋風 | 1808 | 小 |
| 107 | 21 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻五 濡問屋硯 | 1756 | 小 |
| 107 | 22 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻六 暗女昼化物 | 2067 | 小 |
| 107 | 23 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻六 旅泊人詐 | 1397 | 小 |
| 107 | 24 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻六 夜発付声 | 3504 | 中 |
| 107 | 25 | 井原 西鶴 | 好色一代女 巻六 皆思謂五百羅漢 | 1618 | 小 |
文字数合計 50197
名作速読朗読文庫vol.108 好色五人女 Professional版
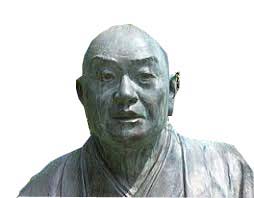
好色五人女(原文)
井原西鶴
内容
好色五人女は、江戸時代の浮世草子で、井原西鶴作、5巻5冊あり、発刊は1686年である。5つの独立した物語になっており、すべて当時、一般に知られていた実話に基づいている。
書名は「好色」と書いてあるが、今の時代の好色とは違う。巻5以外はすべて悲劇的な結末を迎える物語となっており、女性たちは、時には命を賭けて一途な恋を貫いている。しかし、物語の語り口には滑稽や露骨な描写なども多く見られ、現代のいわゆる純愛物とは違うものである 。
本文内容見本
あらすじ
① 姿姫路清十郎物語(お夏清十郎)
室津港の酒造の息子・清十郎は色男で、十四の年から遊郭遊びが絶えず、遊女たちからひっきりなしに恋文を受け取っていた。息子の放蕩ぶりを見るに見かねた父親が遊郭に乗り込み、清十郎に勘当を言い渡してしまった。そのとき、多くの遊女たちは身寄りを失った清十郎を見捨てて去って行ったが、清十郎が最も懇意にした皆川という女郎は清十郎に心中を訴え、結局、一人で自害してしまった。清十郎は自身の行状を猛省し、姫路の但馬屋に奉公することとなり、心を入れ替えてまじめに働いた。但馬屋には主人の妹にお夏という十六の美しい娘がいた。ある夜、清十郎の帯を修繕していると、かつて清十郎が受け取った遊女たちからの恋文が出てきた。お夏はそこに記された、清十郎を慕う一途な文章を片っ端から読んでいくうちに、自分自身が恋の心に満たされてしまい、清十郎を恋い慕うようになってしまった。お夏と、その心を知った清十郎とは互いに恋し合う間柄となり、花見の折に幕の陰で二人は結ばれる。清十郎はその後、大坂に小さな所帯をもって二人で暮らしたいと考え、お夏を盗み出して舟で駈落ちを図った。しかし、舟に乗り合わせた飛脚が状箱を宿に忘れたと言って港に引き返したところ、二人は捕らえられて引き戻されてしまった。ちょうど折り悪く但馬屋では七百両が紛失する事件が置き、清十郎はその嫌疑をかけられて打ち首となり、二十五才で帰らぬ人となった。清十郎の死を知ったお夏は発狂して自害しようとしたが果たせず、説得されて出家し、尼となった。
巻一
姿姫路清十郎物語
恋は闇夜を昼の国
春の海しづかに宝舟の浪枕室津はにきはへる大湊なり爰に酒つくれる商人に和泉清左衛門というあり家栄えて万に 不足なし しかも男子に清十郎とて自然と生つきてむかし男をうつし絵にも増りそのさまうるわしく女の好ぬる風俗十四 の秋より色道に身をなし この津の遊女八十七人有しを いずれかあはざるはなし誓紙千束に つもり爪は手箱にあまり切 せし 黒髪は大綱になわせける これにはりんき深き女もつながるべし 毎日の届文ひとつの山をなし 紋付の送り小袖そのま にかさね捨し 三途川の姥も これみたらば欲をはなれ高麗橋の古手屋もねうちは成まし浮世蔵と戸前に書付てつめ置 けるこのたわけいつの世にあがりを請べし追付勘当帳に付てしまうべしと見る人これをなげきしにやめがたきはこの道その
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.108 好色五人女 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 108 | 1 | 井原 西鶴 | 好色五人女 内容 | 3763 | 中 |
| 108 | 2 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻一 恋は闇夜を昼の国 | 1275 | 小 |
| 108 | 3 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻一 くけ帯よりあらわるる文 | 1507 | 小 |
| 108 | 4 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻一 太皷に寄獅子舞 | 998 | 小 |
| 108 | 5 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻一 状箱は宿に置て来た男 | 1566 | 小 |
| 108 | 6 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻一 命のうちの七百両のかね | 757 | 小 |
| 108 | 7 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻二 恋に泣輪の井戸替 | 1365 | 小 |
| 108 | 8 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻二 踊はくづれ桶夜更て化物 | 1716 | 中 |
| 108 | 9 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻二 京の水もらさぬ中忍て合釘 | 2450 | 小 |
| 108 | 10 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻二 こけらは胸の焼付新世帯 | 1363 | 小 |
| 108 | 11 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻二 木屑の杉楊枝ちょっと先の命 | 1147 | 小 |
| 108 | 12 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻三 姿の関守 | 1951 | 小 |
| 108 | 13 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻三 してやられた枕の夢 | 2147 | 小 |
| 108 | 14 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻三 人をはめたり湖 | 1192 | 小 |
| 108 | 15 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻三 小判しらぬ休み茶屋 | 1774 | 小 |
| 108 | 16 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻三 身のうえの立聞 | 1424 | 小 |
| 108 | 17 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻四 大節季はおもいの闇 | 1489 | 小 |
| 108 | 18 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻四 虫出し神鳴もふんとしかきたる君様 | 1965 | 小 |
| 108 | 19 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻四 雪の夜の情宿 | 1535 | 小 |
| 108 | 20 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻四 世に見をさめの桜 | 1120 | 小 |
| 108 | 21 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻四 様子あっての俄坊主 | 1060 | 小 |
| 108 | 22 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻五 つれ吹の笛竹息のあはれや | 1236 | 小 |
| 108 | 23 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻五 もろきは命の鳥さし | 1195 | 小 |
| 108 | 24 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻五 衆道は両の手に散花 | 1916 | 小 |
| 108 | 25 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻五 情はあちらこちらのちがい | 1003 | 小 |
| 108 | 26 | 井原 西鶴 | 好色五人女 巻五 金銀も持あまってめいわく | 1246 | 小 |
文字数合計 40160
名作速読朗読文庫vol.109 おらが春 Professional版

おらが春(原文)
一茶
内容
おらが春は、俳人小林一茶の俳諧俳文集である 北信濃の柏原 で過ごした1819年 文政2年、一茶57歳の一年間の折々の出来事を読んだ俳句・俳文を、没後25年になる 1852年 嘉永5年に白井一之(いっし)が、刊行したものである。 『おらが春』は、時系列に書き記された日記ではなく、刊行を意図して作られたものである。
本文内容見本
おらが春01
一茶
昔たんごの国普甲寺という所に、深く浄土を願う上人ありけり。としの始は世間祝い事してざざめけば、我もせん迚、大卅日の夜、ひとりつかう小法師に手紙したため渡して、翌の暁にしかじかせよと、きといいをしへて、本堂へとま りにやりぬ。
小法師は元日の旦、いまだ隅々は小闇きに、初鳥の声とおなじくがばと起て、教えのごとく表門を丁々と敲けば、内よりいずこよりと問う時、西方弥陀仏より年始の使僧に候と答ふるよりはやく、上人裸足にておどり出て 、門の扉を左右へさつと開て、小法師を上座に称して、きのうの手紙をとりて、うやうやしくいただきて読でいわく、その世界は衆苦充満に候間はやく我国に来たるべし、聖衆出むかいしてまち入候とよみ終りて、おおおおと泣れけると かや。この上人みずから工み拵えたる悲しみに、みずからなげきつつ、初春の浄衣を絞りて、したたる涙を見て祝うとは、物に狂うさまながら、俗人に対して無情を演るを礼とすると聞からに、仏門においては、いわひの骨張なるべけれ 。
それとはいささか替りて、おのれらは俗塵に埋れて世渡る境界ながら、鶴亀にたぐへての祝尽しも、厄払いの口上めきてそらぞらしく思うからに、から風の吹けばとぶ屑家は、くづ屋のあるべきやうに、門松立てず、煤はかず、雪の 山路の曲り形りに、ことしの春もあなた任せになんむかへける
目出度さもちう位也おらが春 一茶
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.109 おらが春 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 109 | 1 | 小林 一茶 | おらが春 内容 | 203 | 小 |
| 109 | 2 | 小林 一茶 | おらが春01 | 879 | 小 |
| 109 | 3 | 小林 一茶 | おらが春02 | 1856 | 小 |
| 109 | 4 | 小林 一茶 | おらが春03 | 752 | 小 |
| 109 | 5 | 小林 一茶 | おらが春04 | 1782 | 小 |
| 109 | 6 | 小林 一茶 | おらが春05 | 2929 | 小 |
| 109 | 7 | 小林 一茶 | おらが春06 | 1672 | 小 |
| 109 | 8 | 小林 一茶 | おらが春07 | 2051 | 小 |
| 合計冊数 8 文字数合計 12174 | |||||
名作速読朗読文庫vol.110 雨月物語 Professional版
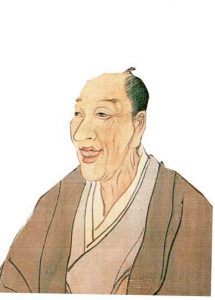
雨月物語(原文+現代語訳)
上田秋成
雨月物語(うげつものがたり)は、上田秋成によって江戸時代後期に著わされた5巻5冊の読物作品である。 日本・中国の古典から進化した怪異小説9篇から成っていて、近世日本文学の代表作 。『雨月物語』は、安永5年4月(1776年)に、出版され,文学史上の位置づけとしては、元禄期と化政期の間、安永・ 天明文化期の、流行が浮世草子から転換しつつあった初期読本にあたる。後には、曲亭馬琴へ強い影 響を与えたといわれている。
内容
白峯(しらみね) – 西行が讃岐国にある在俗時代の主崇徳院の陵墓、白峯陵に参拝したおり、崇徳上皇の亡霊と対面し、論争する。巻之一収録。
菊花の約(きつかのちぎり) – 契りを交わした(衆道)義兄弟との再会の約束を守るため、約束の日の夜、自刃した男が幽霊となって現れる。巻之二収録。
浅茅が宿(あさぢがやど) – 戦乱の世、一旗挙げるため妻と別れて故郷を立ち京に行った男が、7年後に幽霊となった妻と再会する。巻之二収録。
夢応の鯉魚(むおうのりぎよ) – 昏睡状態にある僧侶が夢の中で鯉になって泳ぎまわる。巻之三収録。
吉備津の釜(きびつのかま) – 色好みの夫に浮気され、裏切られた妻が、夫を祟り殺す。巻之三収録。
仏法僧(ぶつぽふそう) – 旅の親子が高野山で、怨霊となった豊臣秀次の一行の宴に遭い、怖い思いをする。巻之三収録。
蛇性の婬(じやせいのいん) – 男が蛇の化身である女につきまとわれるが、最後は道成寺の僧侶に退治される。巻之四収録。
青頭巾(あをづきん) – 稚児に迷い鬼と化した僧侶を、旅の僧である快庵禅師が解脱へと導く。巻之五収録。
貧福論(ひんぷくろん) – 金を大事にする武士、岡左内の寝床に金銭の精が小人の翁となって現れ、金とそれを使う主人との関係を説く。巻之五収録。
本文内容見本
雨月物語 巻之一 原文
白峯
あう坂の関守にゆるされてより。秋こし山の黄葉見過しがたく。浜千鳥の跡ふみつくる鳴海がた。不尽の高嶺の煙 。浮嶋がはら。清見が関。大礒小いその浦々。むらさき艶ふ武蔵野の原塩竃の和たる朝げしき。象潟の蜑が苫や。 佐野の舟梁。木曽の桟橋。心のとどまらぬかたぞなきに。なお西の国の哥枕 見まほしとて。仁安三年の秋は。葭がち る難波を経て。須磨明石の浦ふく風を身にしめつも。行々賛岐の真尾坂の林というにしばらくつえを植む。草枕はるけき旅路の労にもあらで。観念修業の便せし庵なりけり。この里ちかき白峰という所にこそ
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.110 雨月物語 Professional版
| vol | 件数 | 作家 | タイトル | 文字数 | 文章量 |
| 110 | 1 | 上田秋成 | 雨月物語 内容 | 794 | 小 |
| 110 | 2 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之一 白峯 原文 | 5117 | 中 |
| 110 | 3 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之一 菊花の約 原文 | 5493 | 中 |
| 110 | 4 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之二 浅茅が宿 原文 | 5618 | 中 |
| 110 | 5 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之二 夢応の鯉魚 原文 | 2696 | 小 |
| 110 | 6 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之三 吉備津の釜 原文 | 4118 | 中 |
| 110 | 7 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之三 仏法僧 原文 | 5470 | 中 |
| 110 | 8 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之四 蛇性の婬 原文 | 11619 | 大 |
| 110 | 9 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之五 青頭巾 原文 | 4281 | 中 |
| 110 | 10 | 上田秋成 | 雨月物語 巻之五 貧福論 原文 | 4715 | 中 |
文字数合計 49921
名作速読朗読文庫vol.111 良寛歌集 Professional版
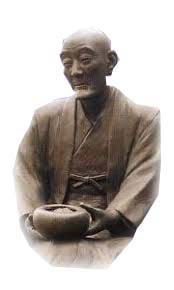
良寛歌集 (原文)
良寛
内容
良寛歌集は 江戸時代後期の曹洞宗の僧侶、歌人、漢詩人、書家である良寛の作品である
良寛は、子供達を愛し、遊んだことが言い継がれている。良寛は「子供の純真な心が誠の仏の心」と考え、子供達と遊び、、かくれんぼや手毬をついたりしたという 名書家として知られた良寛であったが、高名な人物からの書の依頼は断ったが、子供達から「凧に文字を書いて欲しい」と頼まれた時には喜んで字を書いた それは『天上大風』(てんじょうたいふう)で、現存して保存されている
辞世の句
「散る桜 残る桜も 散る桜」 – 太平洋戦争末期に、特攻隊の心情としての歌として有名 「うらをみせ おもてを見せて ちるもみじ」 – 良寛ゆかりの円通寺に句碑がある
本文内容見本
良寛歌集 (原文)1
長歌
五陰皆空と照見して一切の苦厄を度すという心をよめる
世の中は はかなきものぞ あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし世を 百よつぎ 五百代をかけて よろず代に きわめて見れば 枝にえだ ちまたに巷 わかろへて たどるみちなみ 立つらくの たづきも知らず をるらくの すべをも知らず 解き衣の 思いみだれて 浮き雲の 行くへも知らず 言わんすべ 為んすべ知らず 沖にすむ 鴨のはいろの 水鳥の やさかの息を つきいつつ 誰れに向いて
うたえまし 大津のへにいる 大船の へづな解き放ち とも綱とき放ち 大海原のへに おし放つことのごとく をち方や 繁木がもとを やい鎌のとがまもて
うち払うことのごとく 五つのかげを さながらに 五つのかげと 知るときは 心もいれず こともなく わたし尽しぬ 世のことごとも うつし身のうつし心のやまぬかもうまれぬ先にわたしにし身を つの国のなにはのことはよしえやし唯一と足をすすめもろ人
こちらをクリックすると商品がご利用になれます–>
名作速読朗読文庫vol.111 良寛歌集 Professional版
| vol | 件数 | 作家名 | 作品名 | 文字数 | 文章量 |
| 111 | 1 | 良寛 | 内容 目次 | 355 | 小 |
| 111 | 2 | 良寛 | 良寛歌集01 | 2333 | 小 |
| 111 | 3 | 良寛 | 良寛歌集02 | 2925 | 小 |
| 111 | 4 | 良寛 | 良寛歌集03 | 3575 | 中 |
| 111 | 5 | 良寛 | 良寛歌集04 | 5428 | 中 |
| 111 | 6 | 良寛 | 良寛歌集05 | 5474 | 中 |
| 111 | 7 | 良寛 | 良寛歌集06 | 5858 | 中 |
| 111 | 8 | 良寛 | 良寛歌集07 | 5869 | 中 |
| 111 | 9 | 良寛 | 良寛歌集08 | 6103 | 大 |
| 111 | 10 | 良寛 | 良寛歌集09 | 6632 | 大 |
| 111 | 11 | 良寛 | 良寛歌集10 | 10667 | 大 |
| 合計冊数 11 文字数合計 55219 | |||||
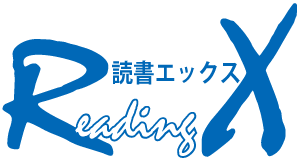

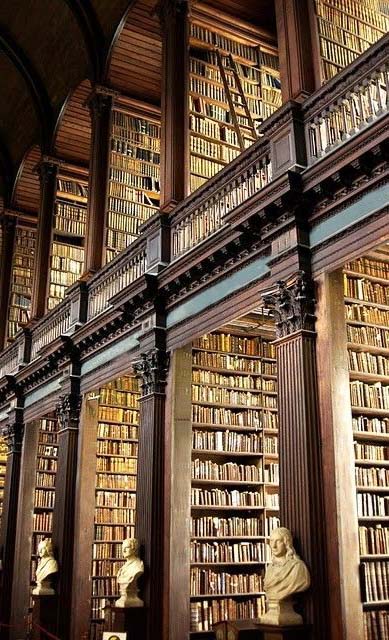
 日本名作速読朗読文庫
日本名作速読朗読文庫